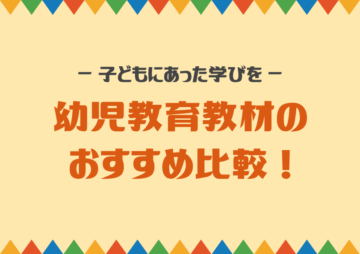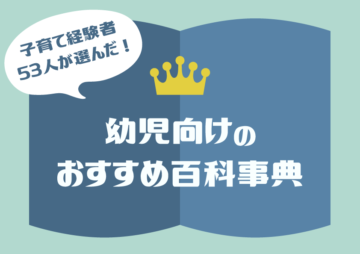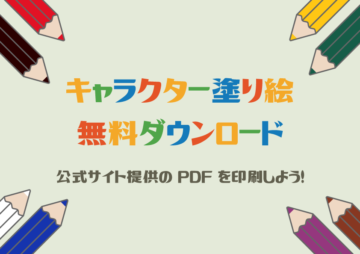【絵本】せかいかえるかいぎ
内容説明
「せかいかえるかいぎ」という会議が開かれるらしい──そんなうわさが、かえるたちの間でささやかれ始めました。このうわさは、かえるたちの歌声に乗ってどんどん広がり、世界中のかえるたちが「ぜひ行ってみよう!」と集まってきます。
いよいよ会議が始まると、かえるたちは「せかいかえるかいぎって何のこと?」「世界中のかえるが集まる会議だよ」「いや、世界を変える会議なんだよ」と、ゲーコゲコと大騒ぎ。そのうち雨が降り出し、かえるたちは雨の中で踊り始めます。そして、たまごからおたまじゃくしが生まれ、会議はますますにぎやかに。結局「せかいかえるかいぎ」の正体は、最後までよくわからないままでした。
この絵本では、モリアオガエルやアマガエル、カジカガエル、ヒキガエル、トノサマガエル、ツチガエル、アフリカウシガエル、ヤドクガエルなど、さまざまな種類のかえるたちが登場します。お話を楽しむだけでなく、図鑑のようにかえるを観察する楽しみ方もできる一冊です。作者の近藤薫美子先生は、昆虫や森の生き物たちを題材にした作品を多く手がける絵本作家。本作でも、世界中のかえるたちをいきいきと描いています。
知育や教材で活用する際のポイント
「せかいかえるかいぎ」は、ユーモアあふれるストーリーと豊かなイラストを通じて、子どもたちの好奇心を刺激する絵本です。この作品を知育や教材として活用する際には、以下のポイントを押さえると効果的です。まず、物語の中でさまざまな種類のかえるが登場するため、生き物に興味を持つきっかけとして活用できます。読み聞かせの際には、「どのかえるが好き?」と問いかけたり、絵本に出てくるかえるを図鑑で調べてみたりすることで、自然や生物への関心を深めることができます。
また、「せかいかえるかいぎ」という言葉遊びの面白さも、この絵本の魅力です。言葉の意味を考えたり、同じような音が重なる言葉を見つけたりする活動を通じて、言語感覚を育むことができます。特に小学生では、タイトルの二重の意味を題材にして、言葉の遊びや表現の工夫について話し合う授業の導入に利用するのもおすすめです。
さらに、物語全体の流れを通じて、集団でのやりとりや多様性について考えるきっかけを提供できます。かえるたちが集まる様子や、雨の中で踊る楽しげな場面など、協力や共存の大切さを感じさせるシーンが多く含まれています。保育や授業では、物語の後に「みんなで何かをするとき、どんな楽しいことがある?」といった話題を共有すると、子どもたち同士の対話や共感が生まれやすいでしょう。
![365日の知育ワーク[無料プリント]](https://365chiiku.com/wp-content/themes/chiiku/assets/images/common/logo.png)