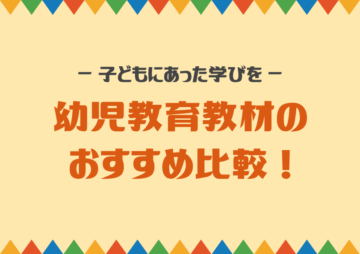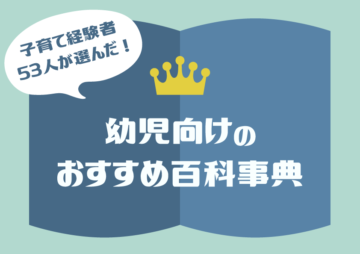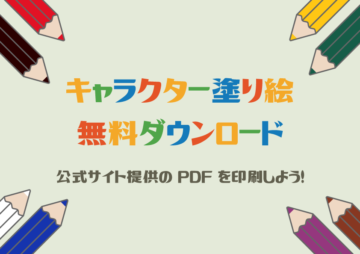【絵本】げんこのキモチ
内容説明
気がつくと、ぼくはいつもこぶしを握りしめ、振り上げていた。それが原因で、おかあさんはぼくを嫌っている。家の中には、ぼくの居場所なんてない。暴力をふるうぼくの拳も、すぐに人をかむ犬のデンの口も、どちらも嫌われ者だから。でも、そんなぼくらは出会い、おたがいを好きになった。そして、ぼくの拳の「キモチ」が少しずつ変わり始めた。
怒りにまかせて暴力をふるってしまうぼくは、ある日、すぐ人をかむ犬と出会う。その犬は、まるでぼくの分身のように感じられ、手放せなくなった。ぼくはその犬を「デン」と名づけ、一緒に暮らし始める。デンが人をかむのには理由があった。その理由は、ぼくが怒りで拳を振るうのとどこか似ている。
ぼくはデンを「かまない犬」にするために懸命に努力するが、その姿はいつもぼくを叱るおかあさんと重なることに気づく。デンに共感しながらも反発し、そして少しずつ変わっていくぼくたち。拒絶される存在が抱える本当の気持ちとはどんなものなのか。そして、相手を心から思いやったとき、どんな行動が生まれるのか。ぼく自身が変わっていく姿を通して、心の奥にある感情を描いたみずみずしい絵本です。
知育や教材で活用する際のポイント
この絵本は、怒りや暴力、拒絶といった感情に向き合いながら、共感や変化を通して成長していく主人公の姿を描いています。子育てや教育の現場では、子どもたちが自分の感情を理解し、他者を思いやる力を育むことが重要ですが、この物語はそのサポートにぴったりの教材となります。
まず、この絵本を読むことで、子どもたちは「怒り」や「拒絶される気持ち」といったテーマに自然に触れることができます。主人公が犬のデンと出会い、お互いに似た部分を認め合いながら変わっていく姿は、共感の大切さを教えてくれます。子どもたちにとって、自分と重ね合わせやすいストーリーが描かれているため、感情の共有や言語化の練習にもつながるでしょう。
また、主人公が「叱る側」としての役割も経験することで、親や先生の立場を疑似的に体験できる点もポイントです。このプロセスを通じて、子どもたちは「叱られる側の気持ち」と「叱る側の気持ち」の両方を考え、行動に責任を持つ意識を養うことができます。この絵本を親子で一緒に読む場合は、読み終えた後に「どうして主人公は変われたのかな?」と問いかけたり、「デンの気持ちを考えてみよう」といった対話をすることで、家庭での感情教育にも役立ちます。
さらに、保育園や小学校で活用する際には、物語をきっかけに「感情カード」などを使ったワークショップを取り入れるのもおすすめです。「怒り」だけでなく「悲しみ」や「喜び」といった感情について皆で話し合うことで、自己理解と他者理解を深める時間をつくることができます。この絵本は、感情教育や共感力の向上を目指す場面で、子どもたちの心に寄り添う貴重な一冊となるでしょう。
![365日の知育ワーク[無料プリント]](https://365chiiku.com/wp-content/themes/chiiku/assets/images/common/logo.png)