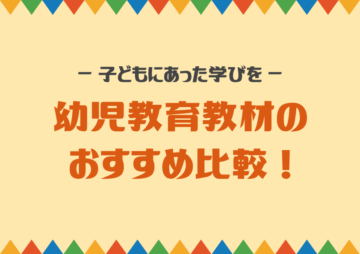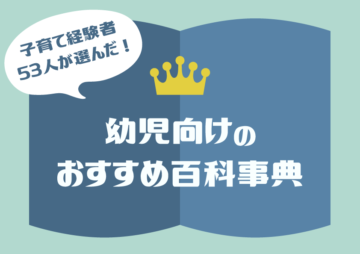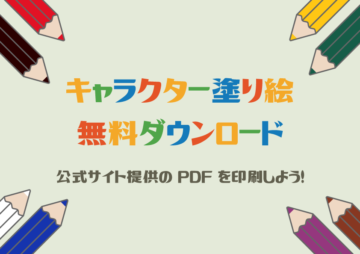【絵本】ほっきょくで うしをうつ
内容説明
「お腹がすいた……。どこかに食べられる動物はいないだろうか」。極寒の地で探し求めた先に姿を現したのは、ジャコウウシの群れ。探検家・角幡唯介が実際に経験した出来事を、阿部海太が力強い絵で描き出しました。
「10年前、私は食べるために初めて生きている動物を殺しました。そのときの鳴き声は、今も耳に残っています」と語る角幡唯介。この絵本は、命を奪うことを避けられない状況での葛藤と、その中で向き合う「死」というテーマを扱っています。
「闇は光の母」シリーズの一作として、谷川俊太郎さんからも推薦されています。「死を重たく考えすぎたくはないが、軽く扱いたくもない」という谷川さんの言葉が示すように、この絵本はただの物語にとどまらず、命や死について深く考えるきっかけを与えてくれます。現代の日本に溢れるさまざまな「死」に関する言葉の中で、この作品は文字と絵を通して新たな問いを投げかけています。
知育や教材で活用する際のポイント
この絵本は、極限の状況で命を奪うという行為に直面した人間の葛藤を描き、命や死について深く考えるきっかけを提供します。子育て世代の親や教育現場の先生がこの絵本を活用する際には、まず子どもたちの年齢や理解度に応じて「命の大切さ」や「自然と人間のつながり」について話す導入を工夫するとよいでしょう。例えば、「私たちが普段食べているお肉や魚も、もともとは生きていた命である」という身近な例から話を始めることで、絵本のテーマを自然に受け入れられる環境を作ることができます。
また、絵本に描かれるリアルな状況や感情は、子どもたちの感受性を強く刺激します。そのため、読み聞かせの後には、「どんな気持ちになった?」「もし自分だったらどうする?」といった問いかけを通して、子どもたちが自分の言葉で考えを表現する時間を持つことが大切です。さらに、命を奪う行為に込められた感情や責任について考える中で、自然の厳しさや他者への感謝の心を学ぶ機会として活用することもできます。
最後に、この絵本は「死」をテーマにしていますが、それは決して重苦しいものではなく、命の循環や生命の尊さを伝えるためのものです。読後は、命のエネルギーが次の命へとつながる自然の仕組みについて話し、絵本が投げかける深い問いを親子やクラス全体で共有しながら考える時間を持つことで、子どもたちの心に長く残る学びを提供できるでしょう。
![365日の知育ワーク[無料プリント]](https://365chiiku.com/wp-content/themes/chiiku/assets/images/common/logo.png)