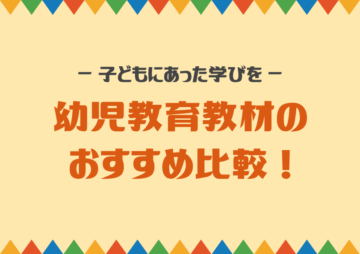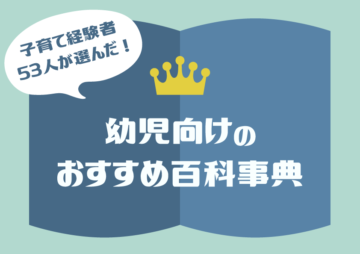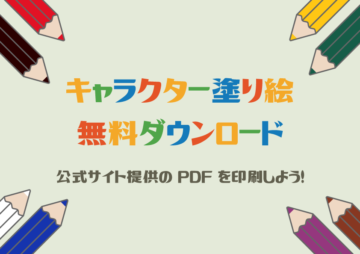【絵本】ぼく
内容説明
「ぼくはしんだ じぶんでしんだ」――90歳を迎える詩人・谷川俊太郎が「自死」をテーマに言葉を紡いだ絵本です。新進気鋭のイラストレーター・合田里美が描き出す美しい日常の風景が、物語をより深く彩っています。
この絵本は、死を重く考えすぎるでもなく、軽く扱うこともせず、真摯に向き合いながら「死」というテーマを見つめた作品です。現代の日本には、死に関する哲学的、宗教的、あるいは商業的な言葉があふれていますが、この絵本はそれとは異なる形で、言葉と絵を通じて「死」と「生」を考えさせてくれます。死を見つめることによって、より良く生きるための道を模索する試みでもあります。
この絵本を読むことで、「ぼく」の心情に共感する人もいるかもしれません。まず最初に伝えたいのは、「どうか生きてください」ということです。抱えている思いは、他人には理解されないと感じるかもしれません。でも、誰かに「自分はこんなふうに感じている」と話してみることで、心が少し軽くなることもあります。ただ、親しい人ほど伝えることにためらいを感じる場合もありますし、周囲に話せる相手がいないと感じることもあるでしょう。そんなときには、国や自治体が設置している相談窓口を活用するという選択肢もあります。「24時間子どもSOSダイヤル」や「全国いのちの電話」、子どものための「チャイルドライン®」など、さまざまなサポートがあります。電話やメールで思いを伝えるのは勇気が必要ですが、誰にも話せない気持ちを少しでも言葉にしてみてください。
この絵本では、「ぼく」が語らなかった声や感情に耳を傾け、「ぼく」の心について考えることを目指しています。友人とのひとときや麦茶の冷たさ、おにぎりの美味しさに思いを馳せる「ぼく」は、きっと本当は生きたかったはず。では、なぜ彼はその選択をしてしまったのか。どうすれば生きられたのか。それを考えることは、「ぼく」がどのように生きたかったのかを考える機会にもなります。そしてその問いは、私たち自身がどう生きていきたいのかを問うことにもつながります。
「ぼく」は私たちのすぐ近くにいる存在かもしれません。あるいは、「ぼく」はもうひとりの自分そのものかもしれません。すべての「ぼく」が、この世界で生き続けられるためにはどうしたら良いのか。この絵本を通じて、そのことを共に考えてみてください。
知育や教材で活用する際のポイント
この絵本は、子どもたちと「生きること」「死」というテーマについて語り合う貴重なきっかけを提供してくれます。死を重くも軽くも捉えず、真摯に向き合った内容は、子どもたちの感性や考え方を育む良い機会と言えるでしょう。親や先生が絵本を通じて自然な形でテーマに触れることで、子どもたちは感情や考えを自由に表現しやすくなります。「どう感じた?」と問いかけることで、子ども自身の言葉を引き出し、内面の気づきをサポートしましょう。
また、絵本に登場する「ぼく」の視点を通じて、日常の小さな喜びや大切な瞬間を再発見することができます。「麦茶の冷たさ」や「おにぎりの美味しさ」といった描写をきっかけに、日常の中で何気なく過ごしていることの価値について子どもたちと話し合うのもおすすめです。こうした対話を通して、感謝や喜びを見つける力が育まれるでしょう。
さらに、この絵本は、他人の気持ちに思いを馳せるきっかけにもなります。「ぼく」が抱えた孤独や葛藤について考えることは、子どもたちが他者に寄り添う力や共感力を育む助けとなります。特に、相手の気持ちを想像することが苦手な年齢の子どもたちには、「『ぼく』はどんな気持ちだったのかな?」と質問しながら、思いやりを育てる時間を作ると良いでしょう。
最後に、この絵本は大人にも深い問いを投げかけています。親や先生自身が絵本を読んだ後、自分の生き方や日常を振り返ることで、子どもたちとの対話により説得力が増すはずです。この絵本を通じて、生きることの尊さについて子どもと共に考え、語り合う時間を大切にしてください。
![365日の知育ワーク[無料プリント]](https://365chiiku.com/wp-content/themes/chiiku/assets/images/common/logo.png)