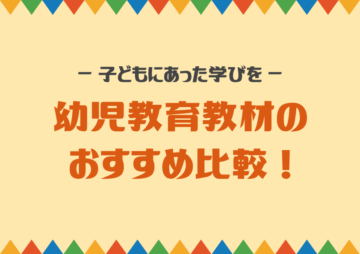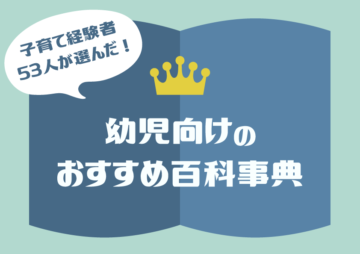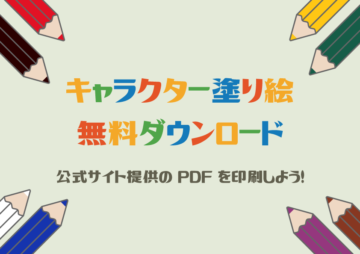【絵本】くまの子ウーフのたからもの
内容説明
どんぐりが「ころりん、すっとんとん」と転がる秋の山で、くまの子ウーフは今日も素敵なものを見つけました。その「たからもの」をポケットに入れたはずなのに、ポケットの穴から「ぽとん、ぽとん」と落ちてしまい、ねずみの袋の中へ入ってしまいます。それでもウーフは気にせず、「またいいものを見つければいいさ」と歩き続けます。
すると今度は、赤くて小さくて、丸くて平たい、きれいなものを見つけました。ウーフの目に映るすべては宝物のようで、その純粋な心が物語を温かく彩ります。
このお話「ウーのたからもの」は、1968年に雑誌で紹介されましたが、翌年の童話集「くまの子ウーフ」には収録されなかった幻の作品です。ウーフの世界観の原点ともいえる、みずみずしく心温まる物語が、広瀬弦の挿絵とともに絵本として生まれ変わります。
知育や教材で活用する際のポイント
「ウーのたからもの」は、子どもたちの「気づく力」や「想像力」を育むのに最適な絵本です。物語の中でくまの子ウーフは、どんぐりや赤くて平たい小さなものなど、日常の何気ないものに価値を見出します。このウーフの姿を通じて、子どもたちに「身の回りにはたくさんの宝物がある」という視点を教えることができます。保育や授業でこの絵本を活用する際は、「ウーフが見つけた宝物をみんなで探してみよう」といった活動を取り入れると、自然観察や創造的な発想を促すきっかけになるでしょう。
また、ウーフがポケットから宝物を失っても前向きな姿勢を崩さない点は、子どもたちに「失敗や損失を乗り越える力」や「ポジティブな考え方」を教える題材として使えます。例えば、子どもたちに「もし宝物をなくしたらどう感じる?」「次はどうする?」と問いかけながら感情を共有することで、共感力や表現力を育むことができます。
さらに、広瀬弦の繊細で温かい挿絵は、視覚的な楽しさも提供し、子どもたちの感性を引き出します。読み聞かせの際には、絵の中に隠れている要素や色使いについて話し合うと、観察力や美的感覚を高める助けとなるでしょう。親や先生が一緒に読み進めながら、子どもたちの発見を褒めることで、自己肯定感を育むこともできます。
![365日の知育ワーク[無料プリント]](https://365chiiku.com/wp-content/themes/chiiku/assets/images/common/logo.png)